
CHANGE DVD-BOX
キムタクのドラマは、いつも面白いと思います。ただ今回のドラマは、ちょっと物足りなさを自分自身では感じました。ドラマとして回がやっぱり10話、11話では、内容が薄く感じましたから。最終回を観た時は、まだ続編のドラマが作れるんじゃないかと思いました。せっかくベテラン勢(豪華)の役者さん方がたくさん出演してますし(余談ですが、車団吉さんなんか久しぶりに観ましたよ(笑))、衆議院解散の総選挙、その後の動向のドラマを観てみたかったからです。最近のドラマは10話〜11話で終るのが、主流なので、仕方ありませんが、TBS「水戸黄門」やテレ朝の「刑事もの」のドラマみたいに半年掛けてドラマを作って欲しかった作品だと自分では、思います。続編が作られると良いなと思いますが、多分、作られないかな(笑)

心のケア――阪神・淡路大震災から東北へ (講談社現代新書)
本書には“カンタンに「ここのケアが大切」などと口にしてはいけない”ということが書いてある。
ノンフィクション作家の最相葉月氏が、東日本大震災の現場に入った精神科医の加藤寛氏に
話を聞くという形でまとめられている。
まず、被災地に入った、精神医療チームが求められたのは、日頃から精神科の投薬をうけている人たちへの
薬の配布であった。
そして、次の仕事が、被災者の話を聴くことだ、私は思っ手本を読み進めたが、加藤氏はこう云う。
「外から精神科の医者が心のケアに来ましたと言ってもちっともありがたがられないです。
精神科にかかること自体にかなり抵抗感があるので、やんわり断られるのがオチです。
他所から来た精神科医や、心理の専門職の人よりも、地域の馴染みの人のほうが力を発揮する。
心の痛手なんてそう他人に話すもんじゃない。聞きっぱなし、いいっぱなしは役に立たない」
「阪神大震災では、こころのケアセンターに60人を採用したが、8割が辞めてしまった。
学校で習ったカウンセリングなんか何の役にも立たない。保健婦さんなら血圧でも測りましょうか
と、話のきっかけを作ることもできるだろうが、心理士にはそんなことも出来ない。
自分には支援ができないとやめた人が8割」
加藤氏は現場で役に立うということに対してあくまでも誠実である。
しかし「心のケア」は、必要で、なぜ必要かもきちんと書いてある。
カウンセラーを目指す人や、メディアで簡単に「心のケア」を口にする人には、
ぜひ読んで欲しい。
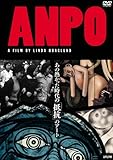
ANPO [DVD]
国を揺るがせた国民的な大闘争が一体なんであったのか。その後の政治は、冷戦のはざまで、一見、逆の方向に進んだかに見えるので、捉え方が非常に難しいはずだ。それを民衆の戦争体験を通して、戦争に反対という一点に焦点を合わせているところに、この映画のユニークさがある。また、映像記録と横尾忠則や山下菊二・池田龍雄など優れた絵画で闘争のエネルギーを再現させている点も。沖縄基地の問題が今もって安保の最大の課題であることも明確に描いている。党派的でない分、クールで、好感が持てた。

異端の系譜―慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス (中公新書ラクレ)
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、通称SFCが1990年に開校してからすでに20年、もうそんなにたったのかという驚きが正直な感想である。日本の大学教育にイノベーションをもたらすべく開校したSFC、なんだか私自身のなかでそのイメージが固定化したまま時間が止まってしまっていたのかもしれない。
本書は、SFCの20年間を、教育分野を専門に追ってきた新聞記者が、幅広い取材のもとに概観したものである。これ一冊でSFCの20年間がわかる内容の一冊となっている。少なくとも、SFC出身でも慶應義塾出身でもない私のような外部の人間にとっては、SFC卒業生は個々に知ることがあっても全体像は知りようがなかった。この一冊ではじめてSFCの全体像をつかむことができたという感想をもつ。
SFCの特徴は、「問題発見・解決型」の人間をつくるという開校以来の教育理念があること、AO入試を最初の段階から実施していることが一般的なイメージとしても定着しているだろう。人生の目的が高校卒業前から明確になっている学生が多いという点が、日本の一般の大学生とは多いに異なる点なのだが、その結果、日本のカイシャ組織では使いにくいという評価も一部では定着してしまった。しかし、自分で考えて自分で行動するという、現在の日本にもっとも必要とされるタイプの人材を早い段階から輩出してきたという点においては高く評価すべきである。ソーシャルビジネスなどにも早い段階から取り組んでいる卒業生たちが多いのはその現れだ。
本書を一読してわかったのは、SFCの特徴は、与えられた専門分野をディシプリンとして教え込むのではない、社会人としての幅広い教養を身につけるためのリベラルアーツ型大学であることだ。講義の選択の自由度が大きいために目的が明確でないと、何も身につかずに卒業してしまうという危険もあるが、むしろ大学院に進学してから専門の勉強をすればいいという米国型の高等教育のあり方に近いのかもしれない。
私は本書によってはじめて、初代学長をつとめた経済学者・加藤寛の伝説的な説なスピーチの存在を知った。第一期の卒業生と同時に学長の座から去った加藤寛のスピーチはSFCの卒業生でなくても感動的である。
本書の取材の範囲は卒業生と教員だけでなく、事務方や他大学の教員など実に幅広い。ナマの声が多数取り込まれているので、SFCの評価を複眼的多面的に知ることができるのも本書の特徴だ。
これから大学進学を考えている高校生やその親御さんだけでなく、日本の将来について考える人にとっても、日本の大学教育に一石を投じたSFCの20年間の軌跡を振り返る意味でも一読する価値はあるだろう。

太陽
音楽好きな人たちの中に起こる議論の一つに「1stアルバムか、2ndアルバムか」というものがある。
例えばオアシス然り、ウィーザー然り。日本で言えば小沢健二なんかがその議論の対象となるであろう(まあ、小沢健二はアルバム自体が非常に少ないアーティストではあるが)。
中村一義もその系譜に入る一人ではないかと思う。「金字塔」か、「太陽」か。人それぞれ好みは異なるし、結局は両方選んでしまう、という人も数多くいると思われるが、個人的には散々悩んだ挙句、この「太陽」を選んでしまう。
「金字塔」との比較について、私は次のように解釈している。
「金字塔」は長い間『他者との関係』を絶ってきた青年が、少しずつその関係を見つめなおしながら「感情が全ての人たちに降り注ぎますように」という慈愛に満ちた決意に至るまでの過程を描いたアルバム。
そして、「太陽」は「金字塔」で決意した『他者との関係』を築こうとして、傷つき、悲しむことがありながらも、自分にとって本当に大切な『他者(これはやはり早苗さんのことではないかと邪推してしまう)との出会い』に至るまでの過程を描いたアルバムであると。
『他者との関係』を築くのは本当に困難である。どうしてこうならないんだろう、とか、何故そんなことを言うんだろう、とか。いつもすれ違いや傷つけあいの連続だ。このアルバムにもそういう場面を切り取った影響からか、揺れ動く感情を描いた曲が多く、とっちらかった印象を抱く人もいるかもしれない(だからこそ誠実なアルバムだと言える)。
しかし、それでも「人を笑わせんのも、泣かせんのも、人」でしかないのだ。生まれた環境も、育ってきた状況も、会ってきた人たちも、それまでの経験も、全て異なる人たちの摩擦でこの世界は動いている。楽しいことばかりではないだろうし、傷つき悲しむこともあるだろう。
その中で、何かを分かち合える『君』に出会えた。こんなに素晴らしいことはない。だから「みんなを待つ誰かや、みんなを待つ誰かも…、出会えるといいな」と中村一義は歌うのだ。
そう、人生と言う名の、世界という名の「列車は走るんだ」。そして、『他者』と出会うことで「生きている」実感を掴んで欲しい。このアルバムを通して、中村一義はそう言っているように聞こえてならない。真の愛に溢れたアルバムである。








